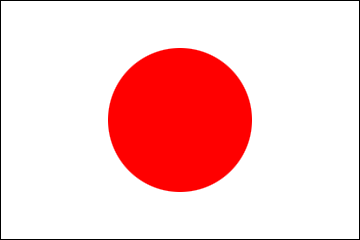重慶モノレール誕生物語
平成30年6月15日
2018年6月15日
在重慶日本国総領事館
首席領事 斎藤憲二
重慶市をはじめて訪問する日本人は、空港から街中へ移動する際、嘉陵江の向かいに映える景色の美しさに一様に感動する。山肌に隙間なく密集する高層ビル群、その間を縫うように走るデザイン豊かなモノレールは、重慶を代表する構図の一つである。在重慶日本国総領事館
首席領事 斎藤憲二
このモノレールの建設にあたり、日中交流の秘話が隠されていることを知る人は、当時のパイオニアたちが勇退していくに伴い、残念ながら年々減っている。重慶における日中交流のシンボルともいえるモノレール誕生物語を末永く記憶にとどめておきたい。そのような思いから、当時の関係資料や関係者からの聞き取りを通じ、その概略をまとめてみたので紹介する。

重慶市の交通事情
実際に目にしたことのある人であれば容易に想像がつくが、重慶市の中心部(特に渝中区)の地形は山の凹凸が激しく、外から見るとまるで香港を思わせるような外観である。坂が多い中に建物が密集しているため、その隙間を縫う道路は狭い上に直線部分がほとんどない。新しく着任した日本人が地理を覚えるのはとても大変だ。ほかの都市ではお馴染みとなっているレンタサイクルも、この場所で見かけることはまずない。多くの都市では、市の中心部といえば特定の一地区をイメージするが、重慶市では多極分散型となっている。これも起伏の多い土地と共存する上での生活の知恵といえよう。
1990年代、重慶市でも自動車が増えつつあり、上記の道路事情もあって交通渋滞や大気汚染問題が深刻化しつつあった。重慶モノレール誕生物語の主人公の一人である瀋暁陽氏(当時:重慶軌道交通総公司総経理)によると、1990年代の国家関連部門による研究評価報告において、重慶は全国22大都市の中で都市公共旅客輸送の総合的な発展水準が後ろから2番目であるとして、早急に立体化の公共交通網を整備すべきと指摘されていたという。
モノレールへの着眼
重慶モノレール誕生の日本側の主役の一人である石川正和氏(当時:日本モノレール協会技術部長。日立製作所KM本部長)は、会報誌の中で、重慶モノレール誕生の発端につきヒントを提供している。石川氏は、1989年に来日した重慶市政府関係者の話として、以前に来日した孫同川・重慶市長が、北九州モノレールに乗車し、すっかりその魅力に見せられ、「将来はこれを重慶市の観光名物にしたい」と述べていたと聞き及んでいる。
石川氏は1989年秋、現地視察のために重慶市を訪問している。が、そのときの結論は「否」。当時想定されていたモノレールのルートは、現在の地下鉄1号線のものであり、トンネルが全体の70%を占めるこのルートでは、モノレールの特性を十分に生かせないと判断したのだ。また当時の重慶市(注:中央直轄市になる8年前)の発展状況を考慮しても、モノレールという最新の交通技術を導入するのは時期尚早ではないかと感じたという。そして、その結果は孫市長にも伝えられた。
モノレールへの執念
しかし、重慶市側はモノレールをあきらめなかった。1991年、重慶市は新都市計画の中で3本の軌道交通ルートを設ける方針を打ち出したが、この時点で、既にモノレールの導入は具体的に念頭にあったようだ。
曲線半径が小さくてすむ、走行騒音が少ない、登坂能力が高い、上部の空間を利用でき道路の中央隔離帯に支柱を建設することで既存の交通施設への影響が少ないなど、モノレールならではの特長が重慶の地形に適していると考えられたからだ。
とはいえ、当時の重慶市において、建設資金の問題は深刻だった。そのため、重慶市の王根芳・公用事業局長が来日し、日本の公的資金を活用することが検討されるようになった。この年、現在の2号線のルートであらためて石川氏に相談が持ちかけられた。今度は嘉陵江沿いに走るルートで、その美景は観光資源としても優位性があり、モノレールに適したものであると思われた。
開通までの道筋
その後の動きは順調だった。1992年12月、国際協力事業団(JICA。現国際協力機構)の専門家による実行可能性調査(F/S)が開始された。10本のルートが候補に上がり、住民外出調査や旅客需要予測から5本に絞られ、最終的に今の2号線ルートが最も適当と決まった。
1994年には国家計画委員会から、重慶市のモノレール交通システム導入の承認が得られた。時期を同じくして、施仲衡・中国工程院院士を団長、瀋暁陽氏(前述)を副団長とする都市交通技術調査団が来日し、都内で都市交通技術座談会を開催したほか、各地で各種のモノレールを視察している。これらを踏まえ、1995年には2010年を見据えた重慶市都市開発指針が策定された。計5本、延べ117kmの軌道交通網を設けるという内容である。
2000年に2号線ルートのF/S報告書が正式に承認され、日本のモノレール方式が採用されることとなった。早速12月には第1期の土木工事(較場口~大堰村14.35km、駅14カ所)が着工する。2001年には日中両政府間で円借款の協議が成立した。その後は、2003年12月に全線の軌道が開通、2004年6月からテスト運行、11月から観光運行、12月28日に第1期工事区間の試運転と進んでいく。そして中央及び重慶市当局の積極的な支援と日中専門家の努力の賜として、重慶市初のモノレール、中国初の跨座型モノレールとなる2号線が、2005年6月18日に正式開通した。
日中の関係機関
モノレール2号線を担当する中国側の政府機関は、軌道交通筹備弁公室(その後、重慶市軌道交通総公司を経て、現在は重慶市軌道交通(集団)有限公司)である。
他方、日本側は以下のような機関が関与した。
・国際協力事業団(JICA。現在の国際協力機構):F/S調査の実施主体
・海外経済協力基金(OECF。海外経済協力基金。現在の国際協力銀行(JBIC)):案件形成促進調査の実施主体
・社団法人海外鉄道技術協力協会(JARTS):システム全般のコンサルティング
・日立製作所:車両、保線用分岐器の納入
・東京モノレール株式会社:スタッフの教育
・日本信号株式会社:信号保安装置の技術指導
また、車両に関しては、「国産化率70%」という中国側ルールを満たすため、日本からは2編成(8両)のみ納入し、残りの車両は日本側が長春軌道客車股份有限公司と技術提携し同工場が製造・納入することになった。
開通までのエピソード
石川正和氏(前述)は、その手記の中で、2号線建設の一連のプロセスにおいて印象深かった点を二つ紹介している。一つは、「人力の凄さ」である。山の斜面や道路橋の下など、極めて難しい工事について、重機による施工しか考えられないと思われていたところが、見事に人力でカバーされた点を感心している。二つ目は「女性の進出」だ。技術分野でも様々な部署で女性が中心になっている姿を見て、日本もこうあるべきと感じたという。
2004年11月、初めて一般乗客を乗せての観光運行が始まった。動物園駅から大坪駅までの5キロ区間で15元の料金を徴収。この距離、バスならば1~1.5元、タクシーでも10元弱というご時世である。市内のあらゆる交通手段の中で、モノレール2号線に乗ることは最も贅沢なものとなった。それにも関わらず、開通時は毎日多くの市民が市場に殺到し、その乗り心地を体験した後は、皆一様にこの新しい乗り物を絶賛した。観光運行は12月末まで続いた。
重慶モノレール2号線は、重慶市最大のプロジェクトであるとともに、中国初の跨座型モノレールであるという点で、大きな注目を浴びた。このプロジェクトに深く関わってきた菅原操・海外鉄道技術協力協会最高顧問(兼日本モノレール協会副会長)は、その功績が認められ、2009年9月、中国政府から国家友誼賞を受賞した。人民日報のインタビューに対し、菅原氏はこう答えている。「今回の受賞は大変名誉であるが、実際の仕事の多くは重慶市軌道交通総公司の人たちが行ったものであり、本当に表彰されるべきは彼らである。」
開業当時の様子
2005年6月18日に2号線の較場口・動物園の区間が正式に営業開始した。この日、動物園駅前において午前9時から約500名の招待客を集め盛大に行われた。中国側は汪光燾・建設部長、姜異康・重慶市党委副書記、王鸿挙・重慶市長、趙公卿・同副市長他が、日本側は岩井敬・国土交通省事務次官、遠藤和也・在中国日本国大使館参事官、富田昌宏・在重慶日本国総領事、菅原操・海外鉄道技術協力協会最高技術顧問、齋藤雅之・東京モノレール社長、金井務・日立製作所会長、千速晃・日中経済協会会長他が出席した。また、北側一雄国土交通大臣及び二階俊博・日本モノレール協会会長(衆議院議員。現自民党幹事長)からのお祝いのメッセージも披露された。式典では、劉景元・重慶市建設委員会元主任による工事報告、来賓の挨拶、テープカットに続き、来賓全員が動物園駅から較場口駅までの試乗を行った。
当時の運賃は最初の3駅で1元、その後4駅ごとに1元ずつアップする設定だった。利用者は開通直後で全日平均3.1万人/日であったが、同年の第4四半期には3.3.万人、2006年に入ってからは4.4.万人と順調に伸びていく。2005年7月1日からは第II期区間(大堰村~新山村)の試運転も開始された。
他地域への経験共有
また2005年の7月21~22日には、重慶市において、モノレール技術の国内外への幅広い普及を目的として「中国・重慶都市モノレール国際シンポジウム」が開催された。中国政府、重慶市、日本モノレール協会、海外鉄道技術協力協会が共催し、中国側事務局を重慶市軌道交通総公司が、日本側事務局を日立製作所が努めた。約500名の参加者の中には、韓国、マレーシア、ドバイなど海外からの人たちも含まれている。中央政府を代表して王铁光・建設部総工程師が、重慶市を代表して何智亚・重慶市人民政府秘書長が、日本側からは富田昌弘・在重慶日本国総領事及び日野祐滋・日本モノレール協会専務理事が、それぞれ挨拶を行った。
2号線沿線の余談
(1)人気スポットとなった李子壩駅
李子壩駅は、20階建てビルの7階にプラットフォームがあり、ビルの壁をモノレールが出入りするユニークな光景が観光スポットとして人気を 集めている。毎日多くの人が写真を撮りに来るので、重慶市政府は専用の展望台を設置する計画である。果たして駅が先だったのか、ビルが先だったのか? 関係者によると、これは山の急斜面という立地条件を勘案し、崖崩れの防止対策と、建設コスト回収の一挙両得を目指し、当初からそのように設計され同時に建設されたものだという。こうした魅力もあって、2号線は開通以来、重慶市民に深く愛されており、建設に携わった日本人技術者にとっても自慢の作品となった。

(2)記念手形碑
仏図関駅の横にある養老施設の壁際に、本件日中協力に関するモニュメントが残っている。2号線の建設に関与した日中双方の数百名の手型と名前が刻まれているほか、完成に至るまでの主要年表も記載されている。今は駐車場の一画と化し目立たない状況であるが、関係各方面の尽力により、重慶市軌道交通(集団)有限公司はこの場所をモノレール建設者記念公園にすることを検討している。


実際に目にしたことのある人であれば容易に想像がつくが、重慶市の中心部(特に渝中区)の地形は山の凹凸が激しく、外から見るとまるで香港を思わせるような外観である。坂が多い中に建物が密集しているため、その隙間を縫う道路は狭い上に直線部分がほとんどない。新しく着任した日本人が地理を覚えるのはとても大変だ。ほかの都市ではお馴染みとなっているレンタサイクルも、この場所で見かけることはまずない。多くの都市では、市の中心部といえば特定の一地区をイメージするが、重慶市では多極分散型となっている。これも起伏の多い土地と共存する上での生活の知恵といえよう。
1990年代、重慶市でも自動車が増えつつあり、上記の道路事情もあって交通渋滞や大気汚染問題が深刻化しつつあった。重慶モノレール誕生物語の主人公の一人である瀋暁陽氏(当時:重慶軌道交通総公司総経理)によると、1990年代の国家関連部門による研究評価報告において、重慶は全国22大都市の中で都市公共旅客輸送の総合的な発展水準が後ろから2番目であるとして、早急に立体化の公共交通網を整備すべきと指摘されていたという。
モノレールへの着眼
重慶モノレール誕生の日本側の主役の一人である石川正和氏(当時:日本モノレール協会技術部長。日立製作所KM本部長)は、会報誌の中で、重慶モノレール誕生の発端につきヒントを提供している。石川氏は、1989年に来日した重慶市政府関係者の話として、以前に来日した孫同川・重慶市長が、北九州モノレールに乗車し、すっかりその魅力に見せられ、「将来はこれを重慶市の観光名物にしたい」と述べていたと聞き及んでいる。
石川氏は1989年秋、現地視察のために重慶市を訪問している。が、そのときの結論は「否」。当時想定されていたモノレールのルートは、現在の地下鉄1号線のものであり、トンネルが全体の70%を占めるこのルートでは、モノレールの特性を十分に生かせないと判断したのだ。また当時の重慶市(注:中央直轄市になる8年前)の発展状況を考慮しても、モノレールという最新の交通技術を導入するのは時期尚早ではないかと感じたという。そして、その結果は孫市長にも伝えられた。
モノレールへの執念
しかし、重慶市側はモノレールをあきらめなかった。1991年、重慶市は新都市計画の中で3本の軌道交通ルートを設ける方針を打ち出したが、この時点で、既にモノレールの導入は具体的に念頭にあったようだ。
曲線半径が小さくてすむ、走行騒音が少ない、登坂能力が高い、上部の空間を利用でき道路の中央隔離帯に支柱を建設することで既存の交通施設への影響が少ないなど、モノレールならではの特長が重慶の地形に適していると考えられたからだ。
とはいえ、当時の重慶市において、建設資金の問題は深刻だった。そのため、重慶市の王根芳・公用事業局長が来日し、日本の公的資金を活用することが検討されるようになった。この年、現在の2号線のルートであらためて石川氏に相談が持ちかけられた。今度は嘉陵江沿いに走るルートで、その美景は観光資源としても優位性があり、モノレールに適したものであると思われた。
開通までの道筋
その後の動きは順調だった。1992年12月、国際協力事業団(JICA。現国際協力機構)の専門家による実行可能性調査(F/S)が開始された。10本のルートが候補に上がり、住民外出調査や旅客需要予測から5本に絞られ、最終的に今の2号線ルートが最も適当と決まった。
1994年には国家計画委員会から、重慶市のモノレール交通システム導入の承認が得られた。時期を同じくして、施仲衡・中国工程院院士を団長、瀋暁陽氏(前述)を副団長とする都市交通技術調査団が来日し、都内で都市交通技術座談会を開催したほか、各地で各種のモノレールを視察している。これらを踏まえ、1995年には2010年を見据えた重慶市都市開発指針が策定された。計5本、延べ117kmの軌道交通網を設けるという内容である。
2000年に2号線ルートのF/S報告書が正式に承認され、日本のモノレール方式が採用されることとなった。早速12月には第1期の土木工事(較場口~大堰村14.35km、駅14カ所)が着工する。2001年には日中両政府間で円借款の協議が成立した。その後は、2003年12月に全線の軌道が開通、2004年6月からテスト運行、11月から観光運行、12月28日に第1期工事区間の試運転と進んでいく。そして中央及び重慶市当局の積極的な支援と日中専門家の努力の賜として、重慶市初のモノレール、中国初の跨座型モノレールとなる2号線が、2005年6月18日に正式開通した。
日中の関係機関
モノレール2号線を担当する中国側の政府機関は、軌道交通筹備弁公室(その後、重慶市軌道交通総公司を経て、現在は重慶市軌道交通(集団)有限公司)である。
他方、日本側は以下のような機関が関与した。
・国際協力事業団(JICA。現在の国際協力機構):F/S調査の実施主体
・海外経済協力基金(OECF。海外経済協力基金。現在の国際協力銀行(JBIC)):案件形成促進調査の実施主体
・社団法人海外鉄道技術協力協会(JARTS):システム全般のコンサルティング
・日立製作所:車両、保線用分岐器の納入
・東京モノレール株式会社:スタッフの教育
・日本信号株式会社:信号保安装置の技術指導
また、車両に関しては、「国産化率70%」という中国側ルールを満たすため、日本からは2編成(8両)のみ納入し、残りの車両は日本側が長春軌道客車股份有限公司と技術提携し同工場が製造・納入することになった。
開通までのエピソード
石川正和氏(前述)は、その手記の中で、2号線建設の一連のプロセスにおいて印象深かった点を二つ紹介している。一つは、「人力の凄さ」である。山の斜面や道路橋の下など、極めて難しい工事について、重機による施工しか考えられないと思われていたところが、見事に人力でカバーされた点を感心している。二つ目は「女性の進出」だ。技術分野でも様々な部署で女性が中心になっている姿を見て、日本もこうあるべきと感じたという。
2004年11月、初めて一般乗客を乗せての観光運行が始まった。動物園駅から大坪駅までの5キロ区間で15元の料金を徴収。この距離、バスならば1~1.5元、タクシーでも10元弱というご時世である。市内のあらゆる交通手段の中で、モノレール2号線に乗ることは最も贅沢なものとなった。それにも関わらず、開通時は毎日多くの市民が市場に殺到し、その乗り心地を体験した後は、皆一様にこの新しい乗り物を絶賛した。観光運行は12月末まで続いた。
重慶モノレール2号線は、重慶市最大のプロジェクトであるとともに、中国初の跨座型モノレールであるという点で、大きな注目を浴びた。このプロジェクトに深く関わってきた菅原操・海外鉄道技術協力協会最高顧問(兼日本モノレール協会副会長)は、その功績が認められ、2009年9月、中国政府から国家友誼賞を受賞した。人民日報のインタビューに対し、菅原氏はこう答えている。「今回の受賞は大変名誉であるが、実際の仕事の多くは重慶市軌道交通総公司の人たちが行ったものであり、本当に表彰されるべきは彼らである。」
開業当時の様子
2005年6月18日に2号線の較場口・動物園の区間が正式に営業開始した。この日、動物園駅前において午前9時から約500名の招待客を集め盛大に行われた。中国側は汪光燾・建設部長、姜異康・重慶市党委副書記、王鸿挙・重慶市長、趙公卿・同副市長他が、日本側は岩井敬・国土交通省事務次官、遠藤和也・在中国日本国大使館参事官、富田昌宏・在重慶日本国総領事、菅原操・海外鉄道技術協力協会最高技術顧問、齋藤雅之・東京モノレール社長、金井務・日立製作所会長、千速晃・日中経済協会会長他が出席した。また、北側一雄国土交通大臣及び二階俊博・日本モノレール協会会長(衆議院議員。現自民党幹事長)からのお祝いのメッセージも披露された。式典では、劉景元・重慶市建設委員会元主任による工事報告、来賓の挨拶、テープカットに続き、来賓全員が動物園駅から較場口駅までの試乗を行った。
当時の運賃は最初の3駅で1元、その後4駅ごとに1元ずつアップする設定だった。利用者は開通直後で全日平均3.1万人/日であったが、同年の第4四半期には3.3.万人、2006年に入ってからは4.4.万人と順調に伸びていく。2005年7月1日からは第II期区間(大堰村~新山村)の試運転も開始された。
他地域への経験共有
また2005年の7月21~22日には、重慶市において、モノレール技術の国内外への幅広い普及を目的として「中国・重慶都市モノレール国際シンポジウム」が開催された。中国政府、重慶市、日本モノレール協会、海外鉄道技術協力協会が共催し、中国側事務局を重慶市軌道交通総公司が、日本側事務局を日立製作所が努めた。約500名の参加者の中には、韓国、マレーシア、ドバイなど海外からの人たちも含まれている。中央政府を代表して王铁光・建設部総工程師が、重慶市を代表して何智亚・重慶市人民政府秘書長が、日本側からは富田昌弘・在重慶日本国総領事及び日野祐滋・日本モノレール協会専務理事が、それぞれ挨拶を行った。
2号線沿線の余談
(1)人気スポットとなった李子壩駅
李子壩駅は、20階建てビルの7階にプラットフォームがあり、ビルの壁をモノレールが出入りするユニークな光景が観光スポットとして人気を 集めている。毎日多くの人が写真を撮りに来るので、重慶市政府は専用の展望台を設置する計画である。果たして駅が先だったのか、ビルが先だったのか? 関係者によると、これは山の急斜面という立地条件を勘案し、崖崩れの防止対策と、建設コスト回収の一挙両得を目指し、当初からそのように設計され同時に建設されたものだという。こうした魅力もあって、2号線は開通以来、重慶市民に深く愛されており、建設に携わった日本人技術者にとっても自慢の作品となった。

(写真は蒋思氏の提供)
(2)記念手形碑
仏図関駅の横にある養老施設の壁際に、本件日中協力に関するモニュメントが残っている。2号線の建設に関与した日中双方の数百名の手型と名前が刻まれているほか、完成に至るまでの主要年表も記載されている。今は駐車場の一画と化し目立たない状況であるが、関係各方面の尽力により、重慶市軌道交通(集団)有限公司はこの場所をモノレール建設者記念公園にすることを検討している。

(3)日中友好の桜
大渡口駅近くの中華美徳公園内に、桜が植樹された一画があり、日中友好の記念碑が残されている。2007年10月27日、日中国交正常化35周年を記念し、日本モノレール協会が500株、重慶市軌道交通総公司が350株、合計850株の桜の苗木が植樹された。日野祐滋・日本モノレール協会専務理事によれば、植樹会には、日本から菅原操・日本モノレール協会副会長他、中国側から余遠牧・重慶市副市長他が出席し、地元中学生の代表、一般市民を含め約300名が参加した。記念碑(「中日友好之樱」)にはこれら経緯が中国語と日本語で刻まれている。
大渡口駅近くの中華美徳公園内に、桜が植樹された一画があり、日中友好の記念碑が残されている。2007年10月27日、日中国交正常化35周年を記念し、日本モノレール協会が500株、重慶市軌道交通総公司が350株、合計850株の桜の苗木が植樹された。日野祐滋・日本モノレール協会専務理事によれば、植樹会には、日本から菅原操・日本モノレール協会副会長他、中国側から余遠牧・重慶市副市長他が出席し、地元中学生の代表、一般市民を含め約300名が参加した。記念碑(「中日友好之樱」)にはこれら経緯が中国語と日本語で刻まれている。

そして未来へ
2018年の労働節の連休(4月29日~5月1日)は、重慶市は中国各地からの若者たちで賑わった。最近、重慶市は「網红城市」(ネット上で盛り上がっている都市)の一つとして人気が急上昇している。重慶市旅遊発展委員会によると、この3日間で重慶市への観光客数は1735万人以上に達した。旅行サイト「携程」(シートリップ)の人気都市ランキングでは、北京、上海に次いで重慶は第3番目にランキングされている。
最近では、重慶を舞台とする映画やドラマもいくつか制作されており、これらも重慶ブームを煽る一因となっている。モノレール2号線が銀幕に登場した最初の作品は、2006年に公開された「瘋狂的石頭」で、その後2016年の「火鍋英雄」と「従你的全世界路過」、2017年の「二次初恋」を通じて、モノレール2号線の存在が多くの人たちに知られるようになった。2018年6月に公開されたばかりの「幸福馬上来」や、日中合作のテレビアニメ作品「重神機パンドーラ」でも重慶がモチーフとして使われており、モノレール2号線は重慶の代名詞の一つとなった。
重慶市軌道交通(集団)有限公司の陳列館の展示によると、最新の重慶市の軌道交通計画は2011年に国務院により批准されたもので、将来、「17路線+1環状線」、延べ820km(うち中心区780km)の軌道交通網が建設される予定とされている。20世紀から21世紀へと時代が移るまさにその瞬間、重慶モノレールという一つの夢に向かい、情熱を注ぎ込み勤勉に汗を流した多くの日本人と中国人が存在した。彼らが蒔いた日中友好と信頼感という種は、モノレール2号線、それに続く3号線の開通という形で見事に発芽し、重慶人の「足」として確実に成長してきた。そして今後、大きな花を咲かせようとしている。本年は日中平和友好条約締結40周年の記念すべき年であり、日中両国民は、井戸を掘った先人たちの思いを胸に、日中友好交流のために地道に水と栄養を与え続けていく使命がある。
注:本稿のまとめに当たっては、日立製作所、日本モノレール協会、鉄道車両輸出組合等の会報誌を参考にした。
(了)
2018年の労働節の連休(4月29日~5月1日)は、重慶市は中国各地からの若者たちで賑わった。最近、重慶市は「網红城市」(ネット上で盛り上がっている都市)の一つとして人気が急上昇している。重慶市旅遊発展委員会によると、この3日間で重慶市への観光客数は1735万人以上に達した。旅行サイト「携程」(シートリップ)の人気都市ランキングでは、北京、上海に次いで重慶は第3番目にランキングされている。
最近では、重慶を舞台とする映画やドラマもいくつか制作されており、これらも重慶ブームを煽る一因となっている。モノレール2号線が銀幕に登場した最初の作品は、2006年に公開された「瘋狂的石頭」で、その後2016年の「火鍋英雄」と「従你的全世界路過」、2017年の「二次初恋」を通じて、モノレール2号線の存在が多くの人たちに知られるようになった。2018年6月に公開されたばかりの「幸福馬上来」や、日中合作のテレビアニメ作品「重神機パンドーラ」でも重慶がモチーフとして使われており、モノレール2号線は重慶の代名詞の一つとなった。
重慶市軌道交通(集団)有限公司の陳列館の展示によると、最新の重慶市の軌道交通計画は2011年に国務院により批准されたもので、将来、「17路線+1環状線」、延べ820km(うち中心区780km)の軌道交通網が建設される予定とされている。20世紀から21世紀へと時代が移るまさにその瞬間、重慶モノレールという一つの夢に向かい、情熱を注ぎ込み勤勉に汗を流した多くの日本人と中国人が存在した。彼らが蒔いた日中友好と信頼感という種は、モノレール2号線、それに続く3号線の開通という形で見事に発芽し、重慶人の「足」として確実に成長してきた。そして今後、大きな花を咲かせようとしている。本年は日中平和友好条約締結40周年の記念すべき年であり、日中両国民は、井戸を掘った先人たちの思いを胸に、日中友好交流のために地道に水と栄養を与え続けていく使命がある。
注:本稿のまとめに当たっては、日立製作所、日本モノレール協会、鉄道車両輸出組合等の会報誌を参考にした。
(了)