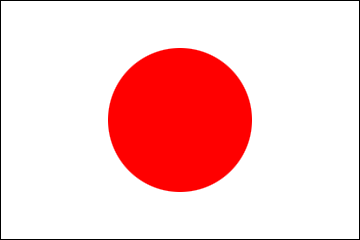S領事の三峡下り体験記
平成30年10月30日
2018年10月、静岡県の旅行社視察団一行に混じり3泊4日の三峡下りツアーに参加した。果たして昔ながらの「三峡下り」は健在なのか?できるだけツアー全体の様子がイメージしてもらえるよう、以下に体験記をご披露したい。
初日の夜。乗船場所は、長江と嘉陵江が合流する朝天門の埠頭。重慶名物の美しい夜景に豪華客船「長江黄金1号」の雄姿が映える。1万トン、乗船人数350人、6階建ての大型船だ。飛行場や駅と同様のパスポート・チェックと荷物検査を経て、いよいよ乗船。豪華な内装に期待感が高まる。「あれっ、昔ツアーに参加した人からは、船内をネズミが駆け回っていたと聞いていたけど、ちょっと様子が違うぞ!」
20時半、出航。各部屋にも小さなデッキがついているが、せっかくなので最上階の展望デッキに出て、去りゆく重慶の光にしばしの別れを告げる。「再見、重慶!」ずっと感傷に浸っていたかったが、思いの外、船風が強く体が冷えてきたので、早々に退散することとした。


2日目。朝、目が覚めると、船は豊都県に停泊していた。2000年の歴史を有し、別名「鬼城」と呼ばれる重慶名所の一つだ。中国語の「鬼」は幽霊の意味。ここでは閻魔大王を祀る名山が観光スポットとなっている。
7時過ぎ、船内のレストランで朝食バイキング。昨晩は気づかなかったが、予想以上に大勢が乗り合わせていて、席はほぼ埋まっている。中国人と外国人の割合は8:2といったところか。
上陸して名山を3時間ほど見学した後、船に戻り昼食。その間に船は出航する。午後はずっと船内なので暇かと思っていたが、操舵室の見学、船長主催歓迎レセプションなどが続き、あっという間に早めの夕食時間になった。いつの間にか、船は忠県に到着していた。
夕食後、上陸してバスに30分揺られ、オプショナルツアー「烽煙三国」を見学に行く。映画村のような場所で、三国志時代のエピソードをテーマとするスペクタクルショーを楽しむ。こんなに巨大な野外ロケのセットは、日本ではまずお目にかかれない。大迫力に圧倒される中、1時間のショーはあっという間に終わった。忠県は以前、石炭の町として有名だったそうだが、今ではこれといった産業も観光資源もない。それだけに、街のはずれに突然現れるこの巨大な舞台装置、なんかギャップ感がすごい。




3日目。寝ている間に船は万州区を通過し、朝食時には奉節県に近づいていた。岸辺に「酒溜移民新村」といった大きな看板が見える。三峡ダムの完成により、ダムから重慶市中心部までの長江約600kmが大きなダム湖と化した。水位は60~90m上がり、水没した場所に住んでいた100万人以上は移民を余儀なくされた。うち重慶市など都市部に移住したのは2割で、残り8割は地元に残り、河岸の山の下から上へと近距離の移動に留まったという。現在、クルーズ船から見える河辺の集落や高層ビルが建ち並ぶ街並みは、ダム建設が始まった後のこの20年で作られたものだ。そんなことに思いを馳せていると、船は奉節県に着いた。ここはネーブルの産地とのこと。朝食後に下船して、目と鼻の先の距離ではあるが、バスで白帝城に移動する。
白帝城は今こそ浮島となっているが、以前は岬に突き出た山城で、2000年前の昔は、中国西南地域を制しようとする武将たちが競って奪おうとした牙城だ。頂上の白帝廟に達するには、水没前は800段の石段を登る必要があったが、今は300段で済むようになった。「ラッキー!」と思いながら歩き始めるが、それでも結構キツイ。山の裏手には、10元紙幣に印刷されている瞿塘峡(くとうきょう)の絶景スポットがある。ここでプロに写真を撮ってもらうと、10元紙幣が2枚必要となる。
11時過ぎに船に戻り、すぐに出航。この瞿塘峡から先が、本当の意味での「三峡下り」となる。絶景の瞿塘峡8kmを約15分で過ぎたところでランチタイムとなる。素晴らしい時間配分だ。そのうちに船は巫山県の波止場に到着した。何となく熱海の雰囲気に似ている!
13時半、小型船に乗り換え、小三峡のクルーズに出発。これは長江に合流する大寧河を遡りまた戻ってくるもので、三峡クルーズの最大の見せ場となっている。水位の上がった今でも十分見応えのある渓谷がひたすら続く。ここで往復4時間。途中、崖の隙間に棺桶(中文:悬棺)を置くという変わった風習の名残も見ることができる。紀元前の昔、あの険しい断崖の途中にどうやって設置したのか、興味は尽きない。
夕方、ちょっと疲れ気味で船に戻るとすぐに出航。18時半頃、第二の峡谷「巫峡」を通過する。残念ながらすでに周囲は暗く、特徴のある頂上部は、闇夜にぼんやりと見えるのみ。峡谷を通過するときは風がとても強く、日本語ガイドさんが大声で「帽子とカツラの方は注意して!」と叫ぶ。夕食が終わると、船内で船員による学芸発表会のようなイベントが行われた。意外におもしろい。



 「重慶の熱海」、巫山の街並み 迫力満点の小三峡
「重慶の熱海」、巫山の街並み 迫力満点の小三峡
最終日、目が覚める頃には、既に最終寄港地の湖北省秭帰(しき)県に到着していた。デッキに出ると、遠くにぼんやりと三峡ダムを眺めることができる。この地は戦国時代の詩人、屈原の生まれ故郷でもある。屈原は端午の節句に粽(ちまき)を食べる風習の由来となった人物とのこと。そういえば昔、そんな話を聞いたことがあるような…。
朝食後、お世話になった「長江黄金1号」にお別れをし、バスで三峡ダム(展望台とダム近辺)見学に向かう。幅2.3km、高さ185m、世界一の水力発電ダムはさすがに雄大。全ての貨物船は、脇に設置されている閘門(こうもん)式水路を通過しなければならない。閘門とは、ダムの上下流の落差を移動するために、段階式に区間を仕切り、その中で水位を調整していく方式。なんと5段ですよ!上海から重慶に水運で運ばれてくる日本食材のありがたさを、しみじみと感じる。
その後、宜昌市に向けて約1時間のバス移動。途中、三番目の峡谷「西陵峡」の一部を車中から見学。ダムの下流域は昔からの景色がそのまま残っている。短時間ながら当時の三峡下りと同じ光景を楽しむことができる。市内ホテルで昼食後、重慶に戻る私は一行と別れ宜昌東駅に向かい、今回の三峡下りの旅は終わりを告げた。

 はるか向こうに三峡ダムを眺む 最終下船地
はるか向こうに三峡ダムを眺む 最終下船地

 貨物船専用の水路 三峡ダム下流の様子
貨物船専用の水路 三峡ダム下流の様子
長江の三峡下りは、桂林の漓江(りこう)下りと並び、中国を代表するクルーズ船ツアーとして、昔から日本人にも人気があった。1993年、三峡ダムの工事が始まるにあたり、旅行社は大々的に「見納めの三峡下り」と銘打って観光客を誘致した。そのため、2009年のダム完成後は、「三峡下り」はもう過去のものとして、日本人観光客の記憶から消えていった。日本語を話すガイドも多くが職を失った。
今回、三峡下りツアーに参加したことで、いくつかのことが分かった。一つは、今でも見応えある風景が十分に残っていること、二つ目は、水位が上がり川幅が広がって水流が緩やかになったおかげで、大型船での航行が可能となり、五つ星ホテルと見まがうほど快適な船内生活を楽しめること、そして三つ目は、観光スポット以外にも、何気ない景色やちょっとした所作の中に、中国らしさを随所に感じることができる点だ。
また、三峡下りの経路には、三国志に縁のある場所も多い。さほど歴史に詳しくなくても、日本ではまだ弥生時代だった頃、劉備や諸葛孔明と いった武将が実際にこの地を走り回っていた…。自分と同じ景色を見ていた…。そんな想像をしてみるだけで、中国の歴史の悠久さを肌で感じることができる。そして、どこでも同じようなモノを売っている土産店を見るにつけ、「商品開発に日本のビジネスチャンスあり!」という淡い期待も抱かせてくれる旅であった。


初日の夜。乗船場所は、長江と嘉陵江が合流する朝天門の埠頭。重慶名物の美しい夜景に豪華客船「長江黄金1号」の雄姿が映える。1万トン、乗船人数350人、6階建ての大型船だ。飛行場や駅と同様のパスポート・チェックと荷物検査を経て、いよいよ乗船。豪華な内装に期待感が高まる。「あれっ、昔ツアーに参加した人からは、船内をネズミが駆け回っていたと聞いていたけど、ちょっと様子が違うぞ!」
20時半、出航。各部屋にも小さなデッキがついているが、せっかくなので最上階の展望デッキに出て、去りゆく重慶の光にしばしの別れを告げる。「再見、重慶!」ずっと感傷に浸っていたかったが、思いの外、船風が強く体が冷えてきたので、早々に退散することとした。


わくわくの長江黄金1号 さらば重慶の夜景!
2日目。朝、目が覚めると、船は豊都県に停泊していた。2000年の歴史を有し、別名「鬼城」と呼ばれる重慶名所の一つだ。中国語の「鬼」は幽霊の意味。ここでは閻魔大王を祀る名山が観光スポットとなっている。
7時過ぎ、船内のレストランで朝食バイキング。昨晩は気づかなかったが、予想以上に大勢が乗り合わせていて、席はほぼ埋まっている。中国人と外国人の割合は8:2といったところか。
上陸して名山を3時間ほど見学した後、船に戻り昼食。その間に船は出航する。午後はずっと船内なので暇かと思っていたが、操舵室の見学、船長主催歓迎レセプションなどが続き、あっという間に早めの夕食時間になった。いつの間にか、船は忠県に到着していた。
夕食後、上陸してバスに30分揺られ、オプショナルツアー「烽煙三国」を見学に行く。映画村のような場所で、三国志時代のエピソードをテーマとするスペクタクルショーを楽しむ。こんなに巨大な野外ロケのセットは、日本ではまずお目にかかれない。大迫力に圧倒される中、1時間のショーはあっという間に終わった。忠県は以前、石炭の町として有名だったそうだが、今ではこれといった産業も観光資源もない。それだけに、街のはずれに突然現れるこの巨大な舞台装置、なんかギャップ感がすごい。


食事会場はほぼ満席 操舵室の見学


いよいよ上陸 壮大な三国志ショー
3日目。寝ている間に船は万州区を通過し、朝食時には奉節県に近づいていた。岸辺に「酒溜移民新村」といった大きな看板が見える。三峡ダムの完成により、ダムから重慶市中心部までの長江約600kmが大きなダム湖と化した。水位は60~90m上がり、水没した場所に住んでいた100万人以上は移民を余儀なくされた。うち重慶市など都市部に移住したのは2割で、残り8割は地元に残り、河岸の山の下から上へと近距離の移動に留まったという。現在、クルーズ船から見える河辺の集落や高層ビルが建ち並ぶ街並みは、ダム建設が始まった後のこの20年で作られたものだ。そんなことに思いを馳せていると、船は奉節県に着いた。ここはネーブルの産地とのこと。朝食後に下船して、目と鼻の先の距離ではあるが、バスで白帝城に移動する。
白帝城は今こそ浮島となっているが、以前は岬に突き出た山城で、2000年前の昔は、中国西南地域を制しようとする武将たちが競って奪おうとした牙城だ。頂上の白帝廟に達するには、水没前は800段の石段を登る必要があったが、今は300段で済むようになった。「ラッキー!」と思いながら歩き始めるが、それでも結構キツイ。山の裏手には、10元紙幣に印刷されている瞿塘峡(くとうきょう)の絶景スポットがある。ここでプロに写真を撮ってもらうと、10元紙幣が2枚必要となる。
11時過ぎに船に戻り、すぐに出航。この瞿塘峡から先が、本当の意味での「三峡下り」となる。絶景の瞿塘峡8kmを約15分で過ぎたところでランチタイムとなる。素晴らしい時間配分だ。そのうちに船は巫山県の波止場に到着した。何となく熱海の雰囲気に似ている!
13時半、小型船に乗り換え、小三峡のクルーズに出発。これは長江に合流する大寧河を遡りまた戻ってくるもので、三峡クルーズの最大の見せ場となっている。水位の上がった今でも十分見応えのある渓谷がひたすら続く。ここで往復4時間。途中、崖の隙間に棺桶(中文:悬棺)を置くという変わった風習の名残も見ることができる。紀元前の昔、あの険しい断崖の途中にどうやって設置したのか、興味は尽きない。
夕方、ちょっと疲れ気味で船に戻るとすぐに出航。18時半頃、第二の峡谷「巫峡」を通過する。残念ながらすでに周囲は暗く、特徴のある頂上部は、闇夜にぼんやりと見えるのみ。峡谷を通過するときは風がとても強く、日本語ガイドさんが大声で「帽子とカツラの方は注意して!」と叫ぶ。夕食が終わると、船内で船員による学芸発表会のようなイベントが行われた。意外におもしろい。


移民新村の看板 白帝城の長い石段


最終日、目が覚める頃には、既に最終寄港地の湖北省秭帰(しき)県に到着していた。デッキに出ると、遠くにぼんやりと三峡ダムを眺めることができる。この地は戦国時代の詩人、屈原の生まれ故郷でもある。屈原は端午の節句に粽(ちまき)を食べる風習の由来となった人物とのこと。そういえば昔、そんな話を聞いたことがあるような…。
朝食後、お世話になった「長江黄金1号」にお別れをし、バスで三峡ダム(展望台とダム近辺)見学に向かう。幅2.3km、高さ185m、世界一の水力発電ダムはさすがに雄大。全ての貨物船は、脇に設置されている閘門(こうもん)式水路を通過しなければならない。閘門とは、ダムの上下流の落差を移動するために、段階式に区間を仕切り、その中で水位を調整していく方式。なんと5段ですよ!上海から重慶に水運で運ばれてくる日本食材のありがたさを、しみじみと感じる。
その後、宜昌市に向けて約1時間のバス移動。途中、三番目の峡谷「西陵峡」の一部を車中から見学。ダムの下流域は昔からの景色がそのまま残っている。短時間ながら当時の三峡下りと同じ光景を楽しむことができる。市内ホテルで昼食後、重慶に戻る私は一行と別れ宜昌東駅に向かい、今回の三峡下りの旅は終わりを告げた。




長江の三峡下りは、桂林の漓江(りこう)下りと並び、中国を代表するクルーズ船ツアーとして、昔から日本人にも人気があった。1993年、三峡ダムの工事が始まるにあたり、旅行社は大々的に「見納めの三峡下り」と銘打って観光客を誘致した。そのため、2009年のダム完成後は、「三峡下り」はもう過去のものとして、日本人観光客の記憶から消えていった。日本語を話すガイドも多くが職を失った。
今回、三峡下りツアーに参加したことで、いくつかのことが分かった。一つは、今でも見応えある風景が十分に残っていること、二つ目は、水位が上がり川幅が広がって水流が緩やかになったおかげで、大型船での航行が可能となり、五つ星ホテルと見まがうほど快適な船内生活を楽しめること、そして三つ目は、観光スポット以外にも、何気ない景色やちょっとした所作の中に、中国らしさを随所に感じることができる点だ。
また、三峡下りの経路には、三国志に縁のある場所も多い。さほど歴史に詳しくなくても、日本ではまだ弥生時代だった頃、劉備や諸葛孔明と いった武将が実際にこの地を走り回っていた…。自分と同じ景色を見ていた…。そんな想像をしてみるだけで、中国の歴史の悠久さを肌で感じることができる。そして、どこでも同じようなモノを売っている土産店を見るにつけ、「商品開発に日本のビジネスチャンスあり!」という淡い期待も抱かせてくれる旅であった。


鬼城での道案内 白帝城でのお土産屋