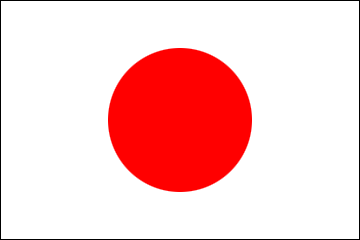四川省概要
令和2年4月2日
1.基本情報
2.歴史
今から3000年以上前の周の時代、「巴国」と「蜀国」が存在しましたが、紀元前316年に秦の支配下に入り、それぞれ「巴郡」、「蜀郡」となりました。紀元前250年に「蜀郡」太守の李氷が水利施設である「都江堰」を築造しました。今なお成都の治水に効果を発揮しており、この工事のおかげで「天府の国」といわれる豊かな農業が発展しました。221年、劉備が成都で帝位につき「蜀漢」を建国しましたが、263年に魏によって滅ぼされました。この興亡の模様は史書『三国志』で知られています。
その後の幾度かの変遷を経て、581年隋の統治下に入りました。隋以降の唐、五代十国時代は四川地域の経済社会が大きく発展した時代でもありました。965年宋による支配を受けた後、1279年に元の統治下に入り「四川行省」(中央政府の地方出先機関)が設置されました。
1363年、元末に「大夏」が建てられましたが、1371年に明の統治下に入り、清の時代に「四川省」が設置されました。明末から清代にかけて頻発した反乱戦争によって四川の経済社会は大きく混乱しました。
1911年の辛亥革命後、成都に四川軍政府が成立しましたが、その後の中華民国初期は、軍閥が割拠して戦争が絶えず、社会的に不安定な時期を迎えました。1937年から1946年までの8年間は、当時の四川省重慶市に国民政府の「戦時首都」が置かれ、抗日戦争時代の重要な後方支援基地となりました。1949年12月より中国共産党による統治が開始されました。
四川の名前は省内を南北に流れて長江に注ぐ四つの川(岷江、沱(トウ)江、涪(フウ)江、大渡河)に由来、成都の名前は蜀の開明王朝が都を移す際、この地は豊かで戦乱が少なかったことから「一年で人が集まり、二年で都に成った」ことに由来する、と言われています。四川省は九寨溝や峨眉山などの景勝地や都江堰、楽山大仏などの観光地、パンダの生息地としても有名です。
(宋王朝時代にはこの地に置かれた成都府路・梓州路・夔州路・利州路(かつての漢中、現在は陝西省)の4つの行政区画を統合して、「川峡四路」と呼ばれる四川路を設置、これより現在までこの地を四川と称する。)
紀元前250年 都江堰築造
221年 劉備が蜀漢建国
1279年 四川行省設置
1937年 四川省重慶市が戦時首都となる
1997年 重慶市など3市1地区が分離し中央直轄市重慶市となる
2007年 成都市が重慶市とともに全国都市農村調和的総合改革試験区として承認
2011年 成都・重慶経済区区域計画が国務院から承認
2014年 「天府新区」が国務院から国家級新区として承認
2017年 自由貿易試験区(FTZ)に指定
2020年 重慶市とともに「成渝地区双城経済圏」の建設を承認
3.気候
(出所:『四川統計年鑑2017』)
※北京:2420.3時間(『中国統計年鑑2016』)、東京:1841.7時間(気象庁HP2016年数値)
4.政治行政組織
★中国共産党四川省委員会
書 記:彭清華
副書記:尹力,鄧小剛
★四川省人民代表大会常務委員会
主 任:彭清華
★四川省人民政府
省 長:尹力
副省長:楊興平、楊洪波、尭斯丹、葉寒氷、李雲澤、王鳳朝
★四川省政治協商会議
主 席:柯尊平
5.主要経済指標
(出所:『四川統計年鑑』各年版等)
6.中国国内における位置づけ
四川省は古来より内陸部有数の穀倉地帯で、それに付随して、食品加工業や紡績工業、製紙業が盛んです。一方で、「三線建設」を契機に、製造業や軍需産業が沿海部などから移転し、今では重慶市と同様に、内陸部有数の工業拠点でもあります。国家級新区である天府新区があり、2017年4月には自由貿易試験区(FTZ)が設置されました。
現在の四川省は、「5+5+1」の産業システム(製造系5、サービス系5、ニューエコノミー1)を重視するとともに、省内各地の産業の棲み分けを行っているのが特徴です。成都を中心としたエリアでは、電子情報、新エネルギー自動車、食品などの産業を、また省東北部では資源を活かした天然ガスの採掘事業、省西南部では鉱物資源を利用した資源開発、省西部では少数民族居住エリアの特色を活かした観光業を中心としています。
中でも成都市の電子情報産業は全国的にも強く、国外(台湾含む)からデル、フォックスコン、インテルなど、国内からレノボ、BOEなど多くのIT関連企業が進出し集積回路やノートパソコン生産などを行っています。2013年からは成都からポーランドに至る国際貨物列車・蓉欧快鉄が運行されています。四川省で生産されたパソコンなどが貨物列車で輸出されており、2019年末までの運行便数は累計で4600便に達し、中国全体の4分の1を占めています。広西チワン自治区を経由し東南アジアに向かう物流ルートも形成されていますが、重慶市が主導し9省市が参加する「陸海新ルート」共同建設には入らず独自路線を歩んでいます。
四川省は石炭や鉄、マンガン、銅、鉛、亜鉛、レアアース、リンなどの埋蔵量が多いことで有名です。また、四川省を含む西南地域はシェールガスの埋蔵量も多いことで知られており、四川省には国家級鉱区の長寧―威遠鉱区があります。
| 位置 | 北緯26度~34度、東経98度~108度 |
| 面積 | 48.5万km2(日本の1.3倍) |
| 人口 | 8341万人(2018年常住人口) |
| 省都 | 成都市 |
| 別称 | 川(Chuan)、蜀(Shu) |
2.歴史
今から3000年以上前の周の時代、「巴国」と「蜀国」が存在しましたが、紀元前316年に秦の支配下に入り、それぞれ「巴郡」、「蜀郡」となりました。紀元前250年に「蜀郡」太守の李氷が水利施設である「都江堰」を築造しました。今なお成都の治水に効果を発揮しており、この工事のおかげで「天府の国」といわれる豊かな農業が発展しました。221年、劉備が成都で帝位につき「蜀漢」を建国しましたが、263年に魏によって滅ぼされました。この興亡の模様は史書『三国志』で知られています。
その後の幾度かの変遷を経て、581年隋の統治下に入りました。隋以降の唐、五代十国時代は四川地域の経済社会が大きく発展した時代でもありました。965年宋による支配を受けた後、1279年に元の統治下に入り「四川行省」(中央政府の地方出先機関)が設置されました。
1363年、元末に「大夏」が建てられましたが、1371年に明の統治下に入り、清の時代に「四川省」が設置されました。明末から清代にかけて頻発した反乱戦争によって四川の経済社会は大きく混乱しました。
1911年の辛亥革命後、成都に四川軍政府が成立しましたが、その後の中華民国初期は、軍閥が割拠して戦争が絶えず、社会的に不安定な時期を迎えました。1937年から1946年までの8年間は、当時の四川省重慶市に国民政府の「戦時首都」が置かれ、抗日戦争時代の重要な後方支援基地となりました。1949年12月より中国共産党による統治が開始されました。
四川の名前は省内を南北に流れて長江に注ぐ四つの川(岷江、沱(トウ)江、涪(フウ)江、大渡河)に由来、成都の名前は蜀の開明王朝が都を移す際、この地は豊かで戦乱が少なかったことから「一年で人が集まり、二年で都に成った」ことに由来する、と言われています。四川省は九寨溝や峨眉山などの景勝地や都江堰、楽山大仏などの観光地、パンダの生息地としても有名です。
(宋王朝時代にはこの地に置かれた成都府路・梓州路・夔州路・利州路(かつての漢中、現在は陝西省)の4つの行政区画を統合して、「川峡四路」と呼ばれる四川路を設置、これより現在までこの地を四川と称する。)
紀元前250年 都江堰築造
221年 劉備が蜀漢建国
1279年 四川行省設置
1937年 四川省重慶市が戦時首都となる
1997年 重慶市など3市1地区が分離し中央直轄市重慶市となる
2007年 成都市が重慶市とともに全国都市農村調和的総合改革試験区として承認
2011年 成都・重慶経済区区域計画が国務院から承認
2014年 「天府新区」が国務院から国家級新区として承認
2017年 自由貿易試験区(FTZ)に指定
2020年 重慶市とともに「成渝地区双城経済圏」の建設を承認
3.気候
| 気候 | 亜熱帯性気候 |
| 年平均気温 | 成都市:16.8度 |
| 年間降水量 | 成都市:983.9mm |
| 平均湿度 | 成都市:82% |
| 年間日照時間 | 成都市:1088.5時間(※) |
※北京:2420.3時間(『中国統計年鑑2016』)、東京:1841.7時間(気象庁HP2016年数値)
4.政治行政組織
★中国共産党四川省委員会
書 記:彭清華
副書記:尹力,鄧小剛
★四川省人民代表大会常務委員会
主 任:彭清華
★四川省人民政府
省 長:尹力
副省長:楊興平、楊洪波、尭斯丹、葉寒氷、李雲澤、王鳳朝
★四川省政治協商会議
主 席:柯尊平
5.主要経済指標
| 指標 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 国内総生産(億元) | 32680 | 36980 | 40678 | 46615 |
| GDP成長率(%) | 7.7 | 8.1 | 8 | 7.5 |
| 1人当たりGDP(元) | 39835 | 44651 | 48883 | 55774 |
| 都市居住者可処分所得 (元/年) |
28335 | 30727 | 33216 | 36154 |
| 農村居住者純収入 (元/年) |
11203 | 12227 | 13331 | 14670 |
| 固定資産投資(億元) | 29126 | 32097 | 28065 | N/A |
| 社会消費品小売総額(億元) | 15501 | 17480 | 18254 | 20144 |
| 対外貿易 輸出(億米ドル) | 279.5 | 375.5 | 503.7 | 563.8 |
| 輸入(億米ドル) | 213.9 | 305.7 | 395.5 | 416.7 |
| 外資直接投資(実行ベース) | 85.5億米ドル | 586億元 | 754.3億元 | 124.8億米ドル |
6.中国国内における位置づけ
四川省は古来より内陸部有数の穀倉地帯で、それに付随して、食品加工業や紡績工業、製紙業が盛んです。一方で、「三線建設」を契機に、製造業や軍需産業が沿海部などから移転し、今では重慶市と同様に、内陸部有数の工業拠点でもあります。国家級新区である天府新区があり、2017年4月には自由貿易試験区(FTZ)が設置されました。
現在の四川省は、「5+5+1」の産業システム(製造系5、サービス系5、ニューエコノミー1)を重視するとともに、省内各地の産業の棲み分けを行っているのが特徴です。成都を中心としたエリアでは、電子情報、新エネルギー自動車、食品などの産業を、また省東北部では資源を活かした天然ガスの採掘事業、省西南部では鉱物資源を利用した資源開発、省西部では少数民族居住エリアの特色を活かした観光業を中心としています。
中でも成都市の電子情報産業は全国的にも強く、国外(台湾含む)からデル、フォックスコン、インテルなど、国内からレノボ、BOEなど多くのIT関連企業が進出し集積回路やノートパソコン生産などを行っています。2013年からは成都からポーランドに至る国際貨物列車・蓉欧快鉄が運行されています。四川省で生産されたパソコンなどが貨物列車で輸出されており、2019年末までの運行便数は累計で4600便に達し、中国全体の4分の1を占めています。広西チワン自治区を経由し東南アジアに向かう物流ルートも形成されていますが、重慶市が主導し9省市が参加する「陸海新ルート」共同建設には入らず独自路線を歩んでいます。
四川省は石炭や鉄、マンガン、銅、鉛、亜鉛、レアアース、リンなどの埋蔵量が多いことで有名です。また、四川省を含む西南地域はシェールガスの埋蔵量も多いことで知られており、四川省には国家級鉱区の長寧―威遠鉱区があります。